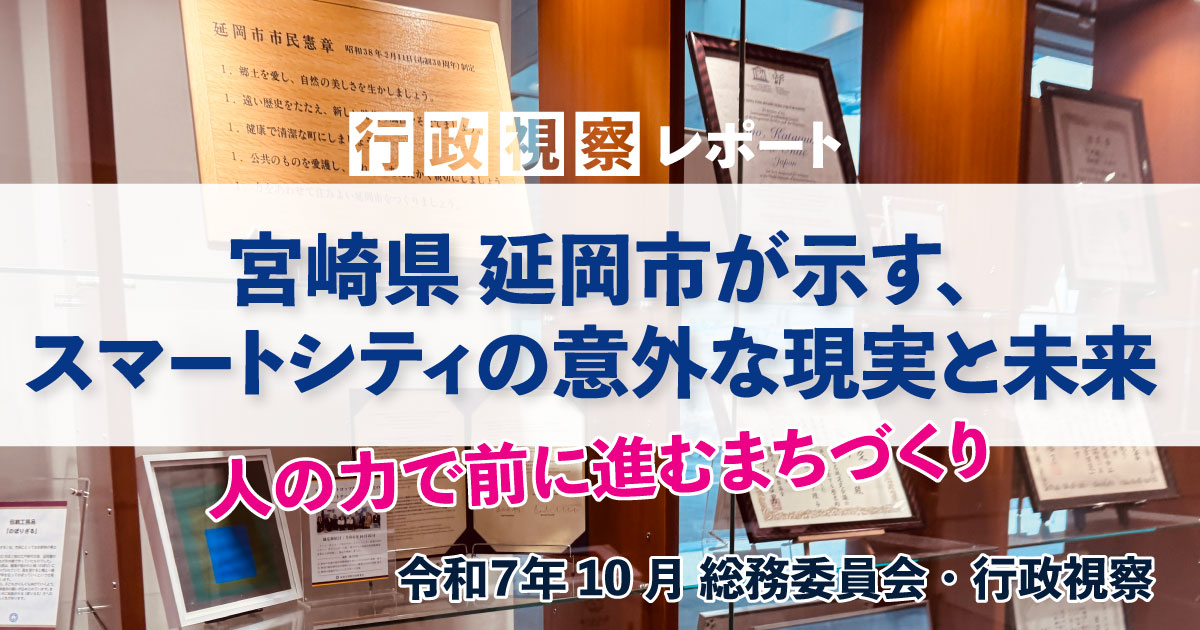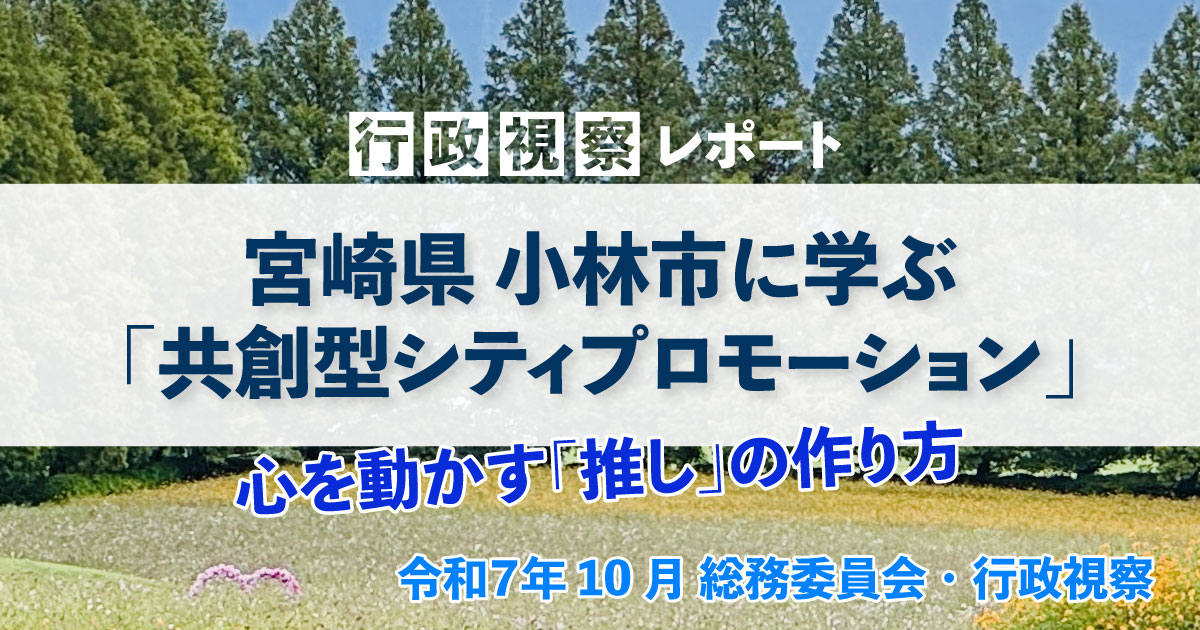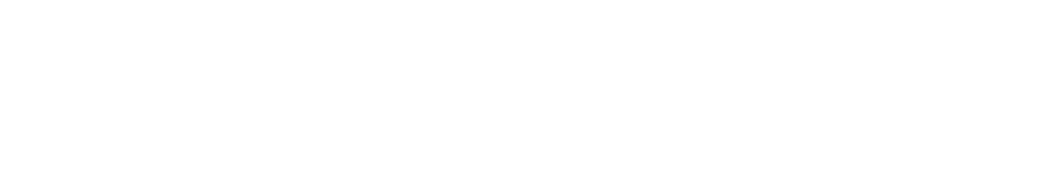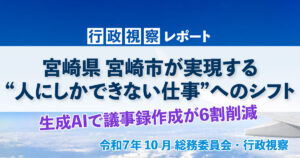令和7年(2025年)10月24日、小平市議会総務委員会の視察最終日は、宮崎県宮崎市。「生成AIの活用や公式アプリの活用など、DX推進」をテーマに行政視察を行いました。

日々の業務報告、終わりの見えない会議の議事録作成…。「デジタル化で仕事が楽になる」と言われて久しいものの、現場ではまだ実感を持ちづらいという声も少なくありません。
そんな中、宮崎県宮崎市が生成AIや公式アプリの活用を通じて、成果を上げていることをご存じでしょうか。今回、総務委員会の行政視察として現地を訪問し、その裏側にある仕組みと考え方を伺ってきました。
宮崎市の事例は、単なる「ツール導入」ではなく、どんな自治体にも応用できる“人中心のDX”のヒントに満ちていました。
AI導入における戦略的な発想
「最先端技術には莫大なコストがかかる」—— そんな常識を覆したのが、宮崎市の生成AI導入です。
Google Cloudおよびソフトバンクとの「共同研究」という枠組みで実施されたため、費用負担を抑えながら実証をスタートできたのです。この連携は単なるコスト削減策ではなく、以前から結んでいた「地域づくりに関する包括連携協定」を土台とする戦略的パートナーシップ。さらに、Google Workspaceとの連携性と、入力データがAIの学習に利用されないクローズドな環境でのセキュリティ確保が決め手となりました。
運用コストは、
- 保守委託契約:約240万円/年
- Google Cloud利用料:約8〜12万円/月
担当者は「この程度のコストでこれだけの成果が出るなら十分に現実的」と話します。DXの壁は「予算」ではなく、むしろ戦略的な発想にあることを示唆しています。創造的な連携を模索することで、「発想の柔軟さ」にあることを実感しました。
議事録作成が6割減。AIが「雑務」を減らし「人にしかできない仕事」を生む
AI導入の最大の成果は、圧倒的な業務効率化です。
議事録作成AIや庁内検索AIを実証的に導入。結果は明確です。
- 議事録作成時間:約60%削減
- 規定検索AIによる効率化:1件あたり平均20分短縮
- 3か月間での業務削減時間:合計約2,113時間
この背景には、宮崎市長の明確な方針があります。
「単純作業でできることはAIに任せ、浮いた時間を市民対応や政策立案に使いなさい。」
AIは単なる効率化の道具ではなく、「人にしかできない仕事」に時間を取り戻すための手段として位置づけられています。
職員の仕事を奪う存在ではなく、人の時間を“本当に価値のある仕事”へと再投資するためのパートナー――その発想が、市の取り組み全体を支えています。
3万ダウンロードの公式アプリに見えた「次の課題」
宮崎市は公式アプリ「Smile Miyazaki」を展開し、プレミアム付き商品券の申請をきっかけに33,948ダウンロードを達成。
しかしその後の分析では、図書館・ごみ分別など日常機能の利用が伸び悩むという課題も見えてきました。
市民モニター調査によると、利用しない理由の上位は
「使いたい機能がない」「利用する機会があまりない」
というシンプルな回答。
市はこれを受けて、地域ポイント機能の導入やお知らせ機能の充実など、日常に根づく改善を検討中です。
アプリの成功はダウンロード数ではなく、生活習慣に溶け込む継続利用にこそあることを示す好例です。
苦手な人を取り残さない。「お助け隊」と研修で支える全員参加のDX
宮崎市では生成AI研修会に300名以上の職員が参加し、実証後には9割以上が継続利用を希望するなど高い受容性を示しました。
背景には、「苦手な人を放置しない」という思想があります。
デジタル支援課の職員による「GWSお助け隊」が、困っている職員のもとへ出向き伴走支援を行うことで、誰も取り残されない体制を築いています。
一方で、「どこまでが機密情報か判断しにくい」という声もあり、今後は運用ルールの明確化が課題とされています。
市はAIを「職員の代替」ではなく、“スーパー職員”を支えるパートナーとして位置づけています。
小平市における「伸びしろ」
今回の宮崎市の取り組みから見えた学びは、以下の3点に集約できます。
- 発想の転換 →「コスト」ではなく「連携」で乗り越える。
- 人中心のDX → AIを“業務効率化”ではなく“創造的再配分”の手段として活用。
- 誰一人取り残さない仕組み → 研修・伴走支援による“全員参加のDX”文化。
小平市でも、すでにLoGoフォームやAI活用などが進みつつありますが、今後は「苦手な職員も安心して挑戦できる環境づくり」や「市民にとってのDX体験の質の向上」が次の伸びしろといえます。本年(令和7年)9月定例会の一般質問では「業務に、もっとAIを」と題して、小平市におけるAI活用について取り上げましたが、AIの活用は職員の働き方改革にとどまりません。市民が行政サービスをより簡単・便利に利用できるようになることこそ、本来の目的です。今後は、申請や相談のプロセスなど、市民が直接触れる部分でのDX体験の質を高めていくことが求められます。
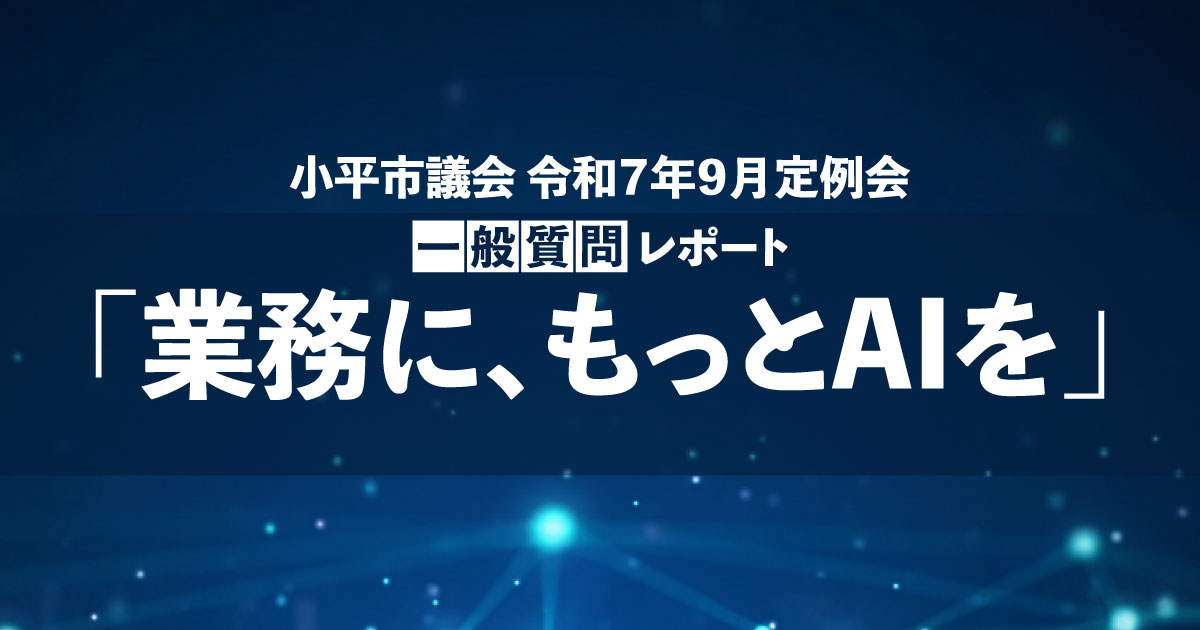
おわりに
宮崎市のDXは、単なる技術導入ではなく「人を中心にした文化改革」でした。
発想力、AIに任せる勇気、誰も取り残さない支援体制。
この三つが揃って初めて、テクノロジーは真の力を発揮します。
「仕事にある『単純作業』をAIに任せるとしたら、どんな『本当に大切な仕事』に時間を使いたいか。」
この問いこそ、これからの自治体DXに求められる視点だと感じました。
今後はこの考え方を、政策提言や議会での議論にも反映させ、AIの導入を「効率化」だけでなく、「人がより良く働ける仕組みづくり」として具体化していきたいと考えています。