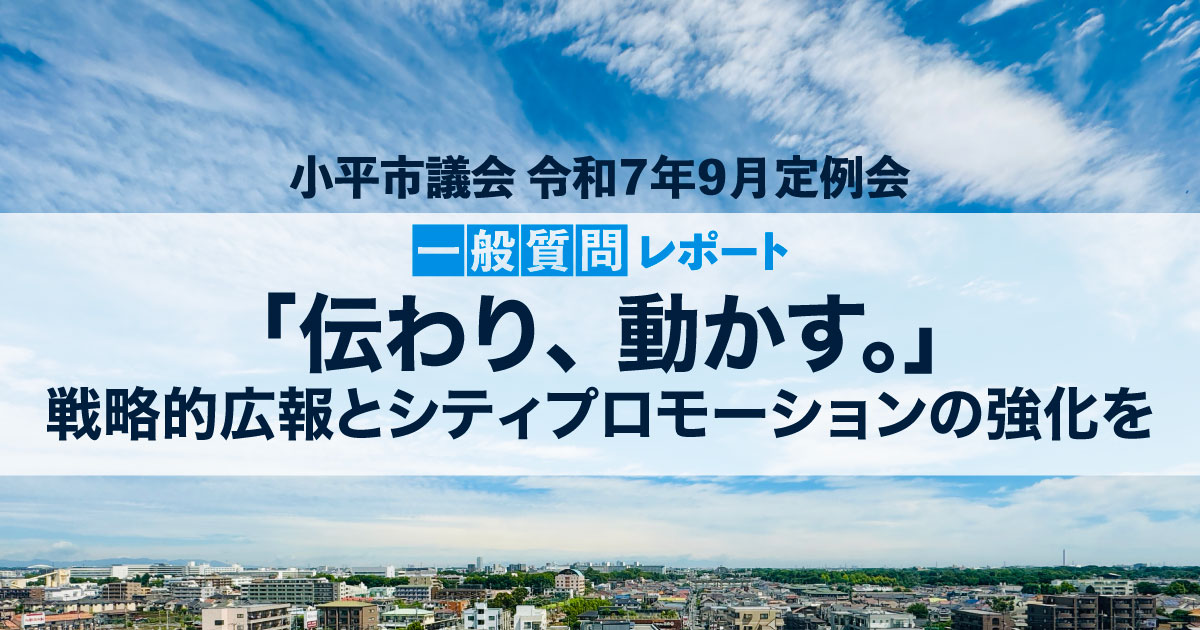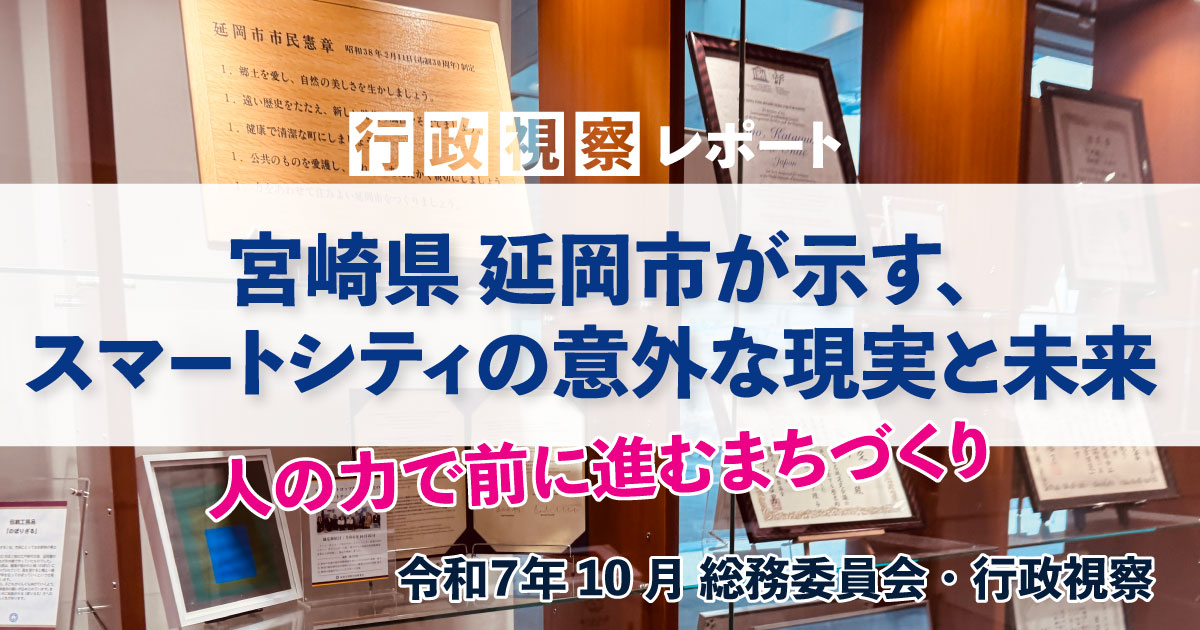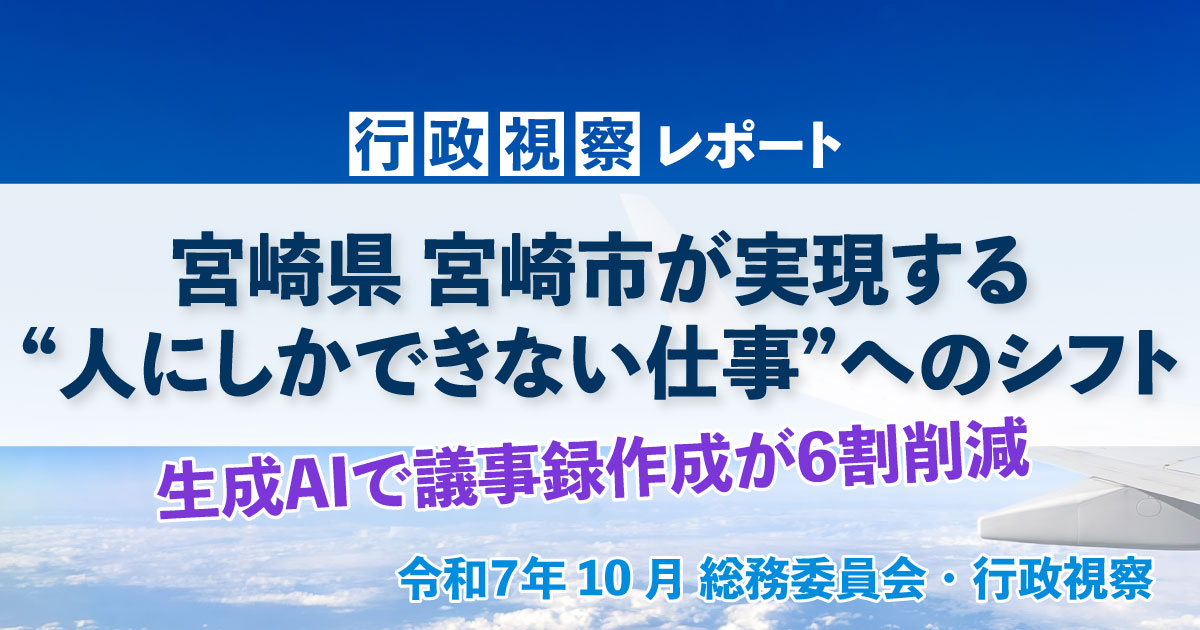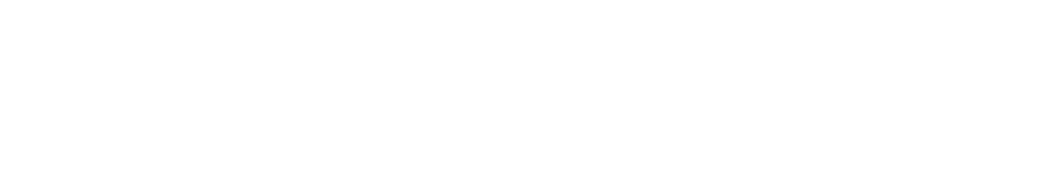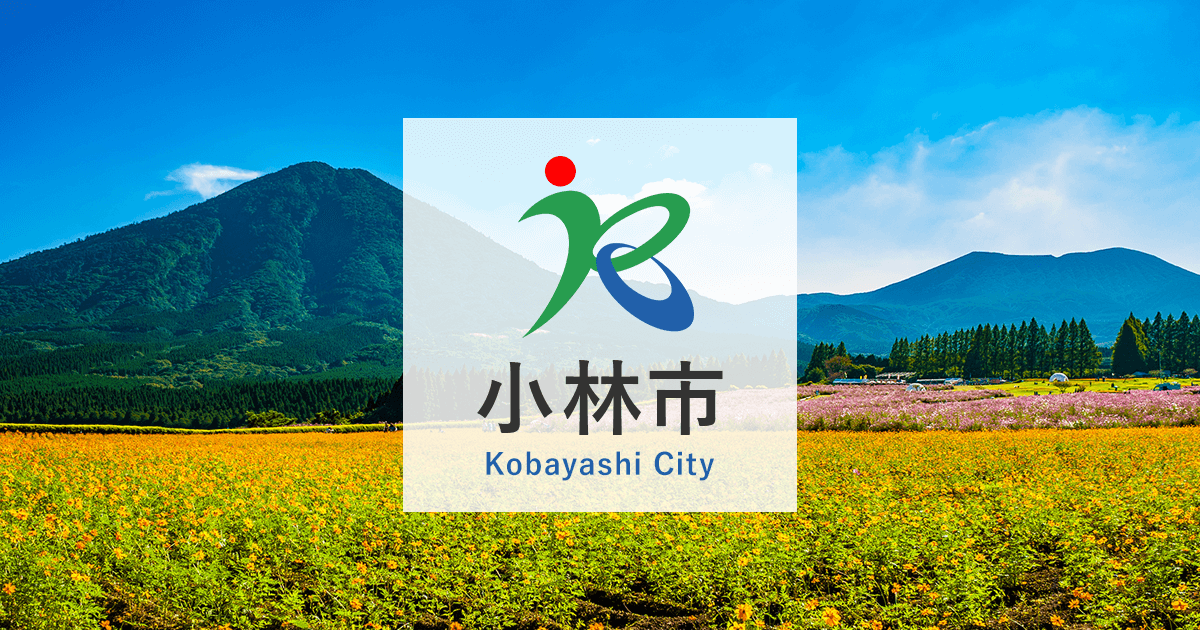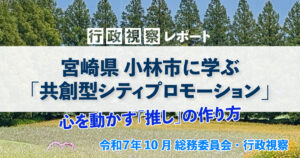小平市議会総務委員会視察2日目の令和7年(2025年)10月23日。宮崎県 小林市を訪れ、「自治体広報・プロモーションの取組」をテーマに行政視察を行いました。

どうすれば、私たちのまちに注目してもらえるのか。
この問いは、今も多くの地方自治体が抱える切実で終わりのないテーマです。宮崎県小林市も、その問いと真剣に向き合っています。約10年前、難解な方言を題材にしたユニークなPR動画「ンダモシタン小林」で全国的な話題を呼びましたが、その熱狂は一時的なものにとどまりました。
しかし近年、小林市は大きな変化を遂げています。広告代理店と組んで「話題づくり」を狙う従来型の手法から、地域に根差した「地に足のついた」発信へと、戦略を大きく転換したのです。新しいアプローチの核心にあるのは、一瞬の「バズ」を狙うことではなく、人々の心を動かし、町への共感や愛着を通じて、継続的なつながりを育むこと。つまり、小林市そのものを「推したくなる存在」にしていく取り組みです。
小林市とはどんなまち?
宮崎県の南西部に位置する小林市は、豊かな自然と美しい水に恵まれたまちです。畜産業が盛んで、宮崎牛は「和牛のオリンピック」で4大会連続の内閣総理大臣賞を受賞。また、名水百選に選ばれた湧水群を活かしたミネラルウォーターやチョウザメ(キャビア)などの特産品も知られています。「霧島連山に抱かれた星空日本一のまち」としても人気があり、豊かな自然と文化がまちの魅力となっています。
「ンダモシタン小林」から「ハッシンコバヤシ」へ 〜挑戦から共創へ、進化するシティプロモーション〜
小林市が注目を集めたきっかけは、2015年の移住促進PR動画『ンダモシタン小林』でした。フランス人が地元の方言・西諸弁を話すというユニークな設定で、「地方創生の成功事例」として全国的に話題に。動画の広告換算効果は約10億円ともいわれています。
この成功を踏まえ、小林市は2022年から第二章となる「ハッシンコバヤシ」プロジェクトを始動。奇抜なアイデアによる“話題づくり”から、市民や出身者とともに進める“共創型の発信”へと舵を切りました。
若者・ファンを動かすPR戦略
かつての「ンダモシタン小林」が全国民という広い層に向けた施策だったのに対し、新しい戦略「ハッシンコバヤシ」は、市出身のアーティストである吉野北人さん(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)や蛙亭イワクラさんを通じ、小林市そのものを「推したくなる存在」という、ターゲットを絞り込むことから始まりました。
この一見ニッチすぎるアプローチは、しかし、絶大な効果を発揮しました。吉野さんと連携した聖地巡礼キャンペーンでは、シーズン1で3,500人、シーズン2では4,000人ものファンが小林市を訪れたのです。驚くべきは、その多くが首都圏や関西圏など、県外からの訪問者だったこと。
これは、マーケティングファネル(認知→興味→行動→共有)を見事に回した結果と言えます。広く浅く万人受けを狙うよりも、「この人のためなら、あの町へ行きたい」と思わせる「狭く、深い」アプローチがいかに強力であるか。そして、それが将来にわたって地域を支える「関係人口」の育成にいかに繋がるかを、この成功は雄弁に物語っています。
THE RAMPAGE・吉野北人さんとのコラボ
- ショートムービー制作: スマートフォンでの視聴に最適化された縦型・短尺の動画を多数制作し、InstagramやTikTokで配信しています。
- 聖地巡礼キャンペーン: 動画のロケ地を巡るデジタルワードラリーを実施し、参加者はトレーディングカードや特産品が当たる抽選に参加できます。
- コラボグッズ開発・販売: 地元事業者と連携し、チャリティ要素(子育て基金への寄付)を含むオリジナルグッズを開発しました。東京・大阪・名古屋などの都市部で期間限定販売会を実施し、長蛇の列ができるほどの盛況となりました。
- 成果:
- 来訪者誘致: 聖地巡礼キャンペーンには、シーズン1で3,500人、シーズン2で4,000人が参加しました。参加者の多くが県外からであり、これまで小林市を訪れることのなかった若い世代を呼び込むことに成功しました。
- SNSでの拡散: ファンがSNS上で自発的に情報を発信することで、二次的なPR効果が生まれています。投稿では「小林市の人が優しかった」という声が多く、市民のホスピタリティが新たな魅力として認識されています。
- 経済効果: グッズ販売売上は初年度で約1,000万円、広告換算費は約2億円と試算されています。
蛙亭イワクラさんとの共演CM
- 小林市出身のお笑いコンビ・蛙亭のイワクラさんもPR大使として活躍。
- 「食」をテーマにした4本のテレビCMシリーズを制作し、イワクラ氏が主演、市民が脇役として多数出演しました。
- 宮崎県内のテレビ局で放映し、周辺地域からの来訪を促進しました。
イワクラ氏は『秘密のケンミンSHOW』など全国ネット番組で、小林市の方言や魅力を自発的に紹介しています。これがきっかけで番組が小林市を特集するなど、市の予算を伴わない大きなPR効果を生んでいます。
市民が主役になる「共創」の仕組み
小林市の特徴は、外への発信だけでなく、内側=市民の意識変化にも力を入れている点です。特に「小林高校生記者クラブ」では、高校生が地域の魅力を自分の言葉で発信。
SNS講座や取材活動を通じて、若者が地域を再発見し、発信者として成長する仕組みが生まれています。
こうした活動が、次世代の郷土愛の育成に繋がっています。
結びに。小平市への示唆
宮崎県小林市のプロモーションは、「認知を取るPR」から「人を動かす共創」へと進化していました。印象的だったのは、「奇抜なアイデア」よりも「挑戦する文化」を育てていることです。初期の成功をきっかけに、「やってみよう」「失敗しても次に活かそう」という前向きな風土が市職員の間に根づいています。広告代理店への丸投げではなく、職員自らが企画・撮影・編集まで手掛ける体制を築いています。こうした「自走型のチームづくり」によって、ノウハウが職員間で蓄積され、持続可能な発信体制が確立されています。そして、市民も“対象”ではなく“共に発信する仲間”として巻き込まれていました。
こうした姿勢が、小林市の情報発信を単なるPRではなく、「まちを一緒につくるプロジェクト」へと発展させているのだと感じます。
小平市でも今後、「誰もが発信者になれる環境づくり」や「市民参加型の情報発信」など、人を中心にした広報のあり方が一層重要になっていくでしょう。小林市のように、行政・市民・出身者が一体となって地域の魅力を形にしていく姿勢は、小平市の広報戦略を考えるうえでも大きなヒントになります。
本年9月定例会では、「戦略的広報とシティプロモーション」について取り上げましたが、まだまだ小平の広報は改善できる点が多くあります。今回の視察で得た学びを、今後の政策提言や議会での議論にしっかりとつなげていきたいと思います。