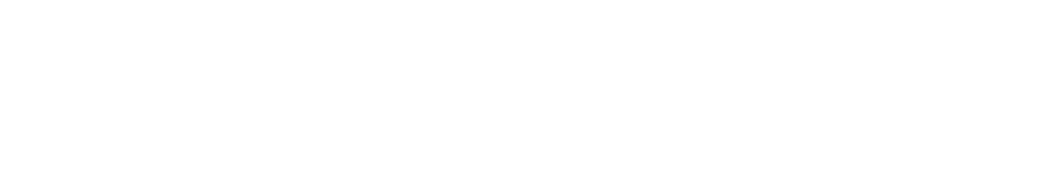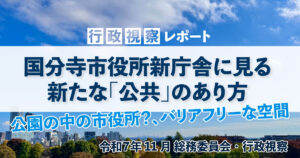令和7年(2025年)11月10日、小平市議会総務委員会で、「国分寺市役所新庁舎」を訪れ、行政視察を行いました。
かつて「市役所」と聞くと、用事がなければ足を運ぶことのない、どこか堅い雰囲気の場所という印象を持つ方も多かったのではないでしょうか。
しかし、2025年1月に開庁した国分寺市新庁舎は、そうした従来のイメージを大きく変えるものでした。単なる行政手続きの場にとどまらず、物理的な垣根や手続きの煩雑さ、そして市民と行政との間にある心理的な壁を取り払うことを目指して設計された、新しいかたちの市役所です。
公園の中の市役所?、バリアフリーな空間

新庁舎と隣接する都立武蔵国分寺公園との間には、多くの公共施設で見られるような塀や柵は一切ありません。代わりに、芝生の広場がゆるやかに庁舎へとつながり、公園と建物がひとつの空間として溶け合うような開放的な景観を形づくっています。まるで庁舎そのものが公園の一部であるかのような一体感が生まれています。
この広場は、市民にとっての憩いの場であると同時に、地域コミュニティの新たな交流の舞台にもなっています。すでにお祭りやイベントなどでの活用が進められており、今後はビアフェスティバルのような新しい企画の相談も寄せられているとのことです。
市民が集う、開かれた玄関とテラス
市役所は本来「事務を行う場」であり、誰もが自由に利用できる「公の施設」ではありません。そうした制約の中で、いかに市民に開かれた場所とするか――その挑戦は庁舎のあちこちに表れており、市民と行政の距離を縮める工夫が多く見られます。
吹き抜けが印象的なメインエントランスの魅力を象徴する出来事が、視察前日の11月9日にありました。屋外で予定されていた音楽イベントが雨で中止になりかけた際、急遽庁舎の広々としたメインエントランスで開催されました。吹き抜けの開放的な空間は音響も良く、2階や3階からも多くの市民が観覧し、大いに盛り上がったとのことです。この出来事は、庁舎が単なる事務スペースにとどまらず、地域の文化活動を支える柔軟な舞台として機能することを示すエピソードです。
さらに、5階の議会フロアには、晴れた日には誰でも自由に利用できる「木漏れ日テラス」があります。「小さなお子さんを連れて訪れ、お茶を飲んだり、子どもが走り回ったりしているんですよ」と職員の方が話してくださいました。そんな家族が、ふと「議会ではどんなことを話しているんだろう?」と、自然な流れで傍聴席に足を運ぶこともあるそうです。
かつての「お堅い議会」という印象をやわらげ、市民の日常と議会活動を地続きにする――そんな優しく開かれた仕掛けがここにはあります。


旧庁舎との比較で見える「身近さ」への変化
旧庁舎の待合スペースは椅子も少なく、議会の傍聴席も限られていました。
しかし新庁舎では、テーブルを備えた広々としたホールやゆとりのある傍聴席が整備され、市民が気軽に立ち寄り、傍聴に訪れる姿が増えているといいます。これにより、議会への関心や参加意識が自然と高まっているとのことです。
新庁舎は、単に快適な空間を提供するだけでなく、市民と行政・議会の間に存在していた「見えない壁」を低くし、人と人とをつなぐ場へと変わりました。その意義は計り知れません。
そして、こうした物理的・心理的な壁を取り払う工夫は、開放的な建築デザインにとどまらず、市民サービスのあり方そのものにも息づいています。
もっと便利に、もっと優しく。市民に寄り添うサービス
新庁舎では、市民サービスをより良くするための仕組みも大きく進化しています。そこには、徹底した市民目線と、理想を描くだけでなく現実の課題にも柔軟に対応していく、しなやかな行政姿勢が息づいています。
食堂を「作らない」という選択
多くの市役所に設けられている食堂が、この新庁舎にはありません。
これは、他自治体で食堂の事業者撤退後に活用されない「デッドスペース」と化してしまった事例を視察した前市長の経験に基づく、意図的な判断です。「食堂はつくらない」という方針のもと、代わりにキッチンカーの誘致や弁当販売の実施といった柔軟な仕組みを導入し、ソフト面で多様な「食の選択肢」を確保しています。
100席以上を備える広々とした交流スペースは、職員と市民の区別なく誰もが利用でき、ランチタイムには満席になるほどの賑わいを見せているとのことです。
固定的な設備に依存せず、時代の変化やニーズに応じて柔軟に対応できる庁舎のあり方を体現していると言えるでしょう。
「ワンストップ窓口」の現実的な挑戦
転入・転出などの手続きの際に、複数の窓口を回らなければならない――。
そんな市民の負担を軽減するために導入されたのが、「ワンストップ窓口」です。

当初の設計段階では、1階の窓口業務と2階の福祉関連部署が連携し、職員がフロアをまたいで対応するという壮大な構想が描かれていました。
しかし、実際の運用では「職員間の連携の難しさ」や「システム面での課題」など、現実的な壁に直面します。
そこで市は、理想の実現を一旦保留し、「市民に負担をかけないこと」を最優先に判断。まずは1階フロア内で完結できる手続きを中心に、確実でスムーズなサービス提供を進めています。
完璧な理想を追うよりも、いま目の前の市民の利便性を優先する――。この現実的で温かい判断こそ、「市民に寄り添う行政姿勢」を体現していると言えるでしょう。そのほか、小平市における窓口改革の参考となる、待たせない、迷わせない工夫も多く実装されていました。


多様な人々への「優しい」配慮
設計段階で障害者団体とのヒアリングを重ねたことで、すべての人が安心して利用できるための細やかな配慮が実現し設計段階で障害者団体とのヒアリングを重ねたことで、すべての人が安心して利用できる細やかな配慮が随所に実現しています。
- カームダウン・クールダウンスペース
パニック障害などを持つ方が人混みを避け、心を落ち着けるための小部屋です。1階と2階に設置され、室内はやや薄暗く静かな空間になっています。空港などでは導入例が増えていますが、市役所としてはまだ珍しい先進的な設備です。 - 広々とした授乳室
おむつ交換シートが3台、プライバシーが確保された個室が4つ備えられ、その規模は大型ショッピングセンター並み。小さな子ども連れの家族も、気兼ねなく庁舎を利用できます。 - 傍聴席の音声サポート
議会傍聴席の床下には、補聴器へ直接音声を届ける「ヒアリングループ」が設置されています。このシステムを納入したのは、市内企業のリオン社。地域企業との連携により、よりインクルーシブな議会参加を実現しています。
日々の利便性を高めるだけでなく、この庁舎は万が一の災害時にも市民を守る、もう一つの重要な役割を備えた建物でもあります。


いざという時、頼りになる。「防災拠点」としての顔
新庁舎の建設地が最終的に決定された「最後の決め手」は、何よりもこの場所が持つ防災拠点としての高いポテンシャルでした。
周辺には災害時に重要な役割を果たす施設が集まっており、新庁舎はそのネットワークに組み込まれることで、まさに“最後のピース”として全体を完成させる存在となっています。
| 施設名 | 災害時の役割 |
|---|---|
| 都立武蔵国分寺公園 | 広域避難所 |
| 国分寺消防署 | 災害対応の中核 |
| 市立小学校 | 地区防災センター |
| いずみプラザ(健康センター) | 要配慮者の災害拠点 |
| 国分寺市役所(新庁舎) | 災害対策本部 |
司令塔である市役所がこの中心に位置することで、各機関との迅速で効果的な連携が可能になります。
即応体制を支える「災害対策本部室」

3階には、災害発生時に指揮の中枢となる「災害対策本部室」が常に待機しています。これは、旧庁舎の狭いスペースでは情報が錯綜し整理もままならなかったという東日本大震災の教訓を徹底的に反映した空間とのことです。
部屋の机の配置は、日常から災害対策本部としての形態を維持しています。災害が発生してから会議室を転用するのではなく、ここは常に「司令室」としてその時を待つ空間なのです。壁一面にはマグネット付きのホワイトボードが設置され、各所から集まる情報を視覚的に整理・共有できます。
正面には100インチの大型モニターが2台。片方では最大8つの民間テレビ放送を同時表示でき、もう片方では市のドローンが撮影するリアルタイム映像の表示も可能です。
情報収集から意思決定まで、迅速かつ的確に行うための万全の備えがここには整っています。
「なり手不足」を解決する警備ロボット
夜間、静まり返った庁舎内を巡回するのは、警備・清掃ロボットです。

この導入の背景には、単なるコスト削減(人件費)の目的だけでなく、より深刻な社会課題があります。それは、警備員の「なり手不足」です。高齢化の進行により、夜間警備を担う人材の確保が難しくなっており、これは国分寺市だけでなく、日本全体が直面する少子高齢化と労働人口減少という課題の縮図とも言えます。
このロボットの年間リース費用は約800万円ですが、夜間警備員にかかる人件費を約1,000万円削減できる見込みです。
テクノロジーの活用によって、労働力不足という社会課題の解決と自治体の財政的メリットの両立を実現した、先進的な事例と言えるでしょう。
結びに:市民と共に未来を創る市役所へ
公園のように開かれた空間は、市民が気軽に立ち寄り、交流できる環境を生み出し、物理的・心理的なバリアを取り除きました。日常の手続きや利用の場面でも、市民に寄り添う利便性と優しさが随所に息づき、誰もが安心して過ごせる空間を提供しています。そして、災害時には頼れる拠点として、市民の生命を守る最後の砦の役割を果たします。
この庁舎は、単に行政サービスを提供する場所にとどまらず、市民の日常に溶け込み、安全を支え、未来を共に創る開かれたプラットフォームへと進化しました。国分寺市の新たな挑戦は、これからの公共施設のあり方を示す一つのモデルとなっています。
小平市も公共施設の更新を迎え、複合化や利活用の工夫が進められています。今回の視察を通じて改めて感じたのは、市役所や公共施設が、用事を済ませるだけの場所から、ふらりと立ち寄りたくなる公園のような場へと変わり、行政と市民の境界線がやわらぐ可能性です。そのような視点を持ちながら、公共のあり方を再考することが求められます。
公共建築は、単なる機能的な「箱」ではなく、人々の行動や意識を変え、コミュニティを育む「触媒」になり得ます。成功例だけでなく、失敗や想定外の出来事からも学び、柔軟に変化していく――そのプロセスの中に、未来の公共空間を考えるヒントが隠されています。
こうした観点を踏まえ、小平市においても、市民が自然に集い、交流し、学び合えるような公共空間の創出や、利用者目線に立ったサービス設計を積極的に進めることが、今後の公共施設づくりにおける重要な指針となると考えています。