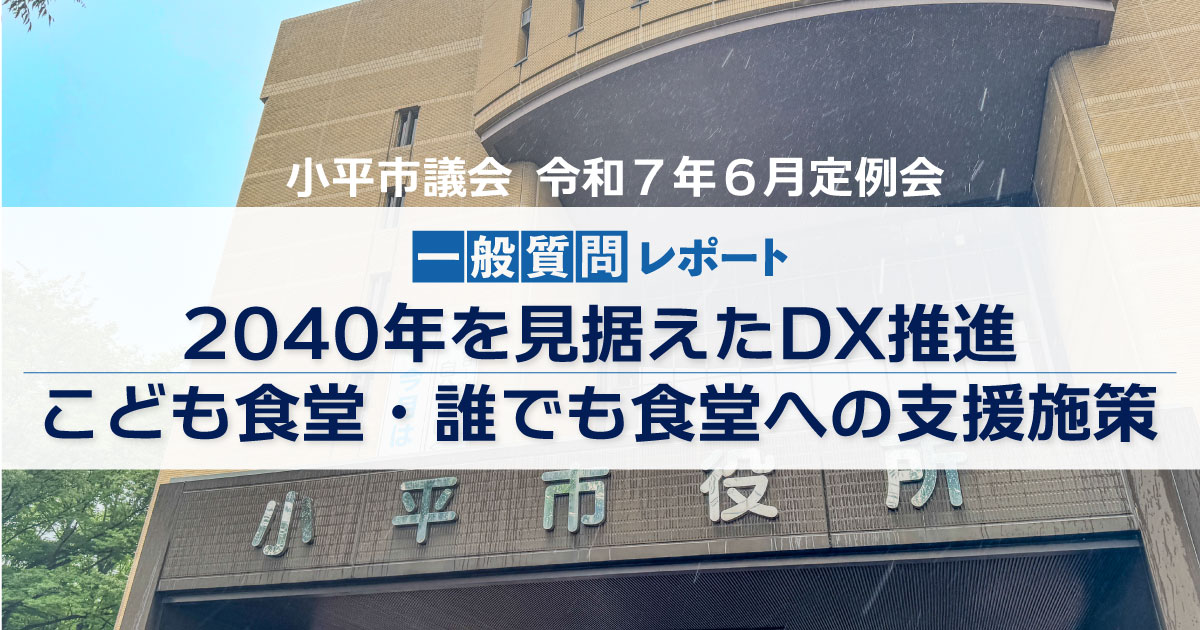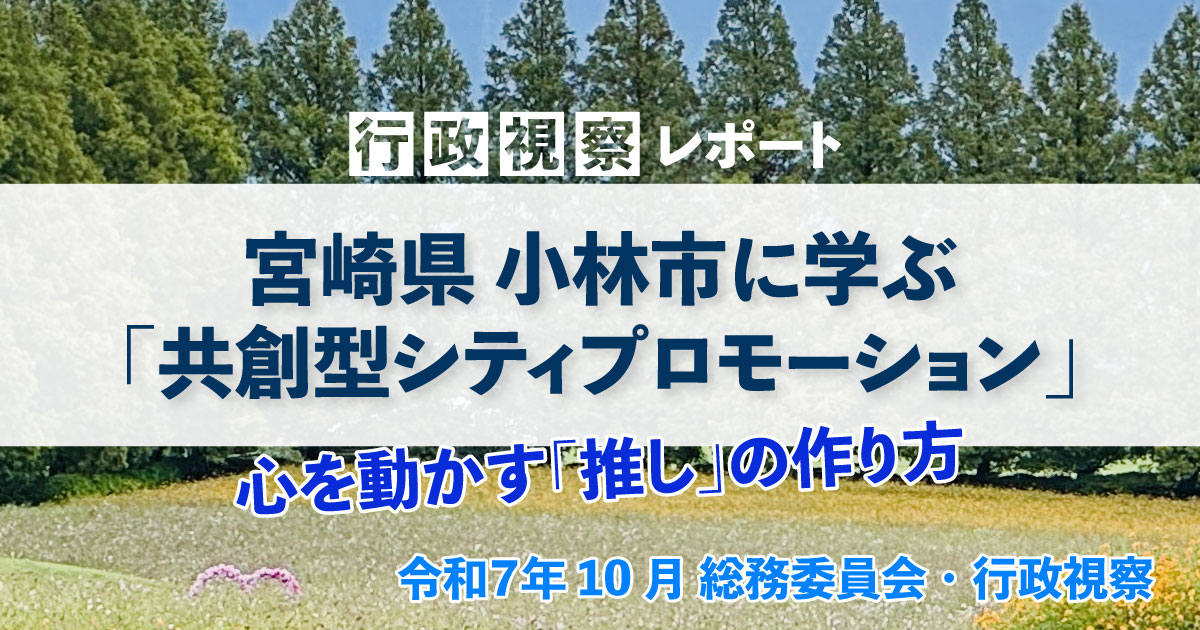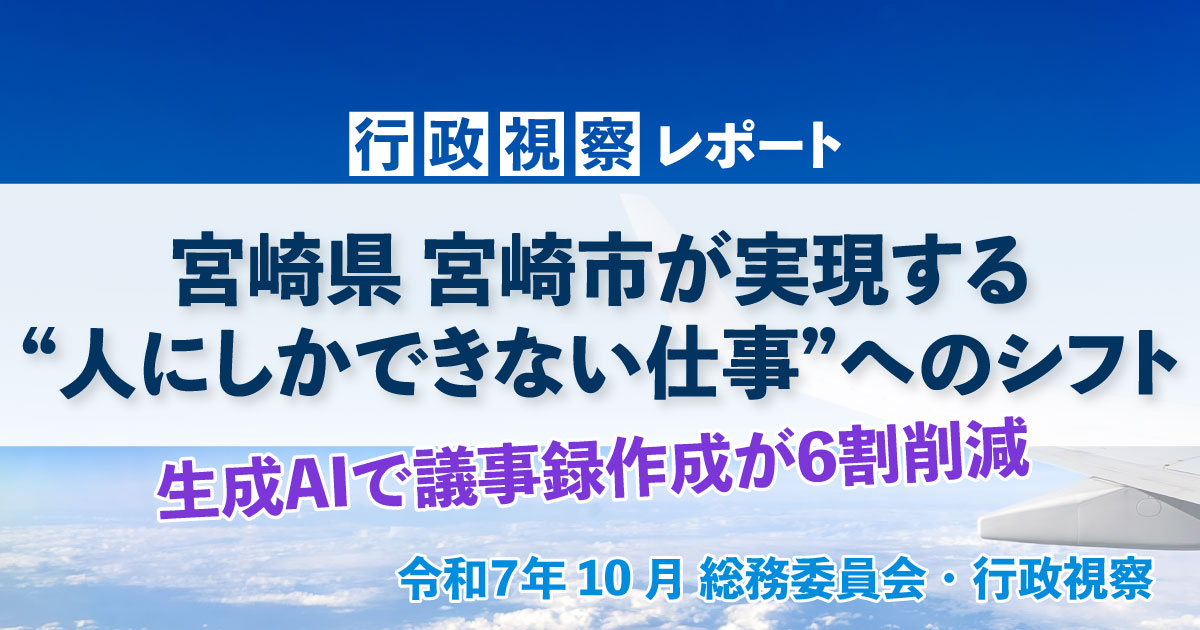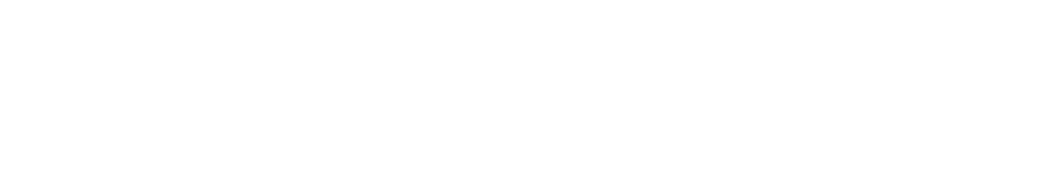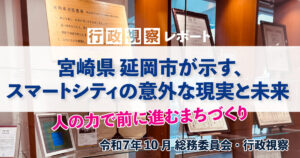令和7年(2025年)10月22日から3日間の日程で、小平市議会総務委員会の視察が行われました。初日は宮崎県 延岡市を訪れ、「スマートシティ・DX推進の取組」をテーマに行政視察を行いました。

「スマートシティ」と聞くと、多くの人は何を思い浮かべるでしょうか。大都市に張り巡らされたセンサー網、AIによる交通最適化、ビッグデータを活用した未来予測――。そんなSF映画のような光景をイメージするかもしれません。
しかし、本当に注目すべきスマートシティの最前線、その本質は、地域が抱えるリアルで切実な課題を、テクノロジーでいかに解決するかにあります。その最たる例が、宮崎県延岡市の挑戦です。
延岡市の取り組みの根底には、2009年に医師の一斉退職によって地域医療が崩壊しかけたという、街の存続を揺るがすほどの危機がありました。この経験から生まれた強烈な「市民力」が、今なお市のデジタル変革を駆動しています。彼らの野心的なプロジェクトは、国が推進する「デジタル田園都市国家構想交付金」といった財源を戦略的に活用し、地方都市が直面する課題解決の新たなモデルを提示しています。
救急医療の「空白地帯」を埋める、空飛ぶクルマの挑戦
延岡市のスマートシティ戦略を象徴するのが「空飛ぶ救急車」構想ですが、これは単なる未来技術への憧れではありません。かつての医療崩壊というトラウマへの、直接的なアンサーなのです。
市はドクターヘリの基地病院から遠く、救命率を大きく左右するとされる「15分ルール」(要請から15分以内に現場に到着する目安)の範囲外に位置しています。隣接する熊本県や大分県のドクターヘリ基地からも離れており、まさに救急医療の「空白地帯」。この生命に関わる課題を解決するため、市が打ち出したのが「空飛ぶクルマ(電動垂直離着陸機:eVTOL)」の導入でした。これは夢物語ではなく、5カ年計画で進められている現実的なプロジェクトです。
もちろん、いきなり空飛ぶクルマが導入されるわけではありません。その第一歩として、市はすでに救急車と病院がリアルタイムで患者情報を共有する「QaaSシステム」を構築・運用しています。これは「総合救急アズアサービス」の略で、救急車内で取得した心電図やバイタルデータ、現場の映像などを搬送先の病院に送り、医師が到着前から的確な指示を出せるようにする仕組みです。この通信基盤こそ、将来の「空飛ぶ救急車」に不可欠な土台となります。地域の命を救うという切実な課題が、最先端技術の導入を本気で推し進める原動力となっています。
平時は「おもてなし」、有事は「命綱」。一石二鳥の防災ネットワーク
近年の能登半島地震でも明らかになったように、大規模災害時には携帯電話や光回線といった既存の通信インフラが寸断され、情報が途絶するリスクが常に存在します。
この課題に対し、延岡市は国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が開発した、既存の通信網から独立して機能する通信ネットワーク「NerveNet(ナーブネット)」を導入しました。災害時には市内の避難所で無料Wi-Fiを提供し、被災した住民が家族の安否確認などを行える「命綱」となります。
しかし、このネットワークの最も賢い点は、その活用法にあります。災害時にしか使わない高価なインフラを「遊ばせておく」のではなく、平常時にも積極的に活用しているのです。
具体的には、市を訪れる観光客や出張者向けに無料Wi-Fiを提供。利用時のアンケートに回答してもらうと、市内で使える地域通貨「のべおかCOIN」が付与される仕組みです。これにより、災害対策インフラが、平時には観光振興やマーケティングデータの収集ツールへと姿を変えます。高コストなインフラ投資を平時にも活かすことで、持続可能なモデルを構築している点は、高く評価されるべき独創的なアイデアと言えるでしょう。
最先端技術より難しい、「自分ごと化」という最大の壁
スマートシティの推進において、最も難しいのは技術開発そのものではないのかもしれません。むしろ、導入したテクノロジーを市民に「使ってもらう」ことこそが、最大の壁となることがあります。延岡市の事例は、この逆説的な真実を浮き彫りにします。
市は、市民向けの健康管理・救急連携アプリ「ウィズウェルネス」を開発・提供しています。日々の健康データを記録し、いざという時にはその情報を救急隊と共有できる画期的なサービスですが、現在の登録者数は250〜300名と、決して多いとは言えないのが現状です。その理由を象徴するのが、市民説明会で聞かれた次のような言葉でした。
「自分は救急車に乗ることはない」
この言葉は、かつて地域医療を守るために団結した「市民力」とは対照的な、興味深い心理を示しています。危機に際しては「みんなで」立ち上がる集合的・受動的な力は強い一方で、平時における「個人の」予防医療という能動的な行動変容を促すことの難しさです。多くの市民にとって、救急搬送はまだ「他人ごと」なのです。
実は、あの「空飛ぶクルマ」構想も、当初は「夢物語だ」と否定的な声が少なくありませんでした。しかし、実証実験としての試験飛行を市民の目の前で行うなどの地道な活動を通じて、その認知度と理解は着実に広まっていきました。この経験は、どんなに優れた技術も、市民の理解と参加なくしては真価を発揮できないという、スマートシティ推進における普遍的な教訓を教えてくれます。
結びに:延岡市が示す「本当のDX」と、小平市への示唆
延岡市の挑戦を紐解くと、その取り組みが単なる技術の導入ありきではなく、地域が抱える「救急医療の空白地帯」「災害時の通信途絶」といった、リアルで切実な課題から出発していることがわかります。
そして、市のプレゼンテーションで語られた最も重要なメッセージは、「デジタルがあれば片っ端からやれ、という考え方からの脱却」という視点でした。市の担当者は、ひとつの思考実験として、駅の改札をより高性能なものに更新するのではなく、「そもそも改札をなくす」という発想の転換(パラダイムシフト)が重要だと指摘しています。これは延岡市の計画ではありませんが、問題の根本を問い直す姿勢を象徴しています。
本年6月には、「2040年を見据えたDX推進」をテーマに一般質問を行いました。小平市のDXは、単なるデジタル技術の導入にとどまらず、スマートシティの実現を見据えながら、テクノロジーをどう使うかだけでなく、それによって社会の“当たり前”をどう変えていけるかに焦点を当てていく必要があります。今後も、そうした視点を大切にしながら、政策提言や議会での議論を通じて、持続可能で人にやさしいデジタル社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。