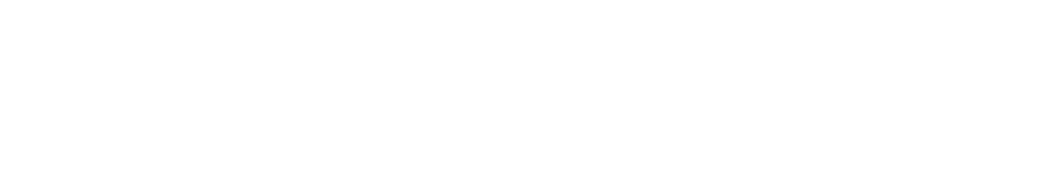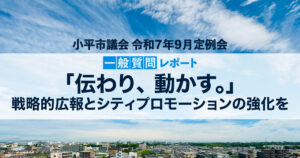戦略的広報で市の魅力を引き出し、未来を創る
行政の情報発信は、もはや単に情報を「伝える」だけでは不十分です。市民の関心や行動を喚起し、地域への愛着や誇りを育む「伝わり、動かす」広報へと進化させていく必要があります。
とりわけ、人口減少や都市間競争が激化する現代において、広報は市民サービスの一環という枠を超え、小平市の未来を左右する重要な戦略です。小平市が持つ豊かな緑や住みやすさといった、市民の暮らしやすさや働きやすさにつながる魅力を最大限に引き出し、市外からの「人口流入」や「企業誘致」につなげるためのシティプロモーションは、まちの活力を維持するために不可欠な役割を担っています。
今回の質問では、こうした認識のもと、「選ばれるまち」という目標を達成するため、市が「具体的なゴール」をどう描いているのか、そしてそれを実現するための「専門的な広報戦略」の策定など、どのように広報やシティプロモーションを進めていくかという方向性を問いました。併せて、伝わり、動かす広報に向けた1つの方法としてウェブサイトの改善に着目し、「最先端の方法論の活用」をどう進めていくのかを問いました。小平市の未来を創るために、広報・シティプロモーションの強化は待ったなしの課題だと考え、このテーマを取り上げました。
広報やシティプロモーションに具体的なゴール設定を

「人口流入、定住、企業誘致」といった具体的な波及効果をゴールとして設定することが不可欠では?
- 単なる「愛着」「イメージ向上」といった抽象的な目標にとどまらず、例えば「子育て・教育で選ばれる小平」という市長の初心表明を具現化する場合など、より明確な方向性を示すべきだと提言しました。
市の答弁から見えたこと
「シティプロモーションや戦略的広報は常に進化し続けるため、ゴールを設定するものではない」との答弁があり、まずは小平市が持つ「緑が豊かで住みやすい」といった財産を市民や市外の人に知ってもらい、良いイメージを持ってもらうことに重点を置くとのことでした。
私は、具体的な目標・ゴールの設定は、
- シティプロモーションへの方向性を定め、限られた経営資源を投入する上では不可欠
- 広報活動の評価や改善につながる
と考えています。市民や外部の人に「小平市を選んでもらう」ためには、単なる周知活動や抽象的なイメージ戦略を超えた明確な目標と、行動計画・戦略が必要です。この点については、次の基本戦略の策定の部分でも取り上げています。
広報・プロモーションの「基本戦略」策定と専門的な推進体制の整備を



シティプロモーションの基本戦略をつくり、人材育成や専門人材の登用など、推進体制を強化すべき
- 市の広報活動ガイドラインは手法を定めたものに過ぎず、シティプロモーション全体の方向性や目標を示す「基本戦略」の策定が必要では。
- 広報担当者だけでなく、全職員の「広報マインド」を高めるため、コミュニケーション戦略やマーケティング分析など、プロモーション専門家による「専門的な研修」の実施を。
- 近隣自治体の事例を挙げ、市全体のプロモーションを強化するために専門人材の登用を。
市長が所信表明で示したシティプロモーションの「強化」という方針を実現するためには、戦略や推進体制の整備が不可欠であると考え、以上のような提案を行いました。
市の答弁から見えたこと
市からは、市長が掲げる「戦略的広報」を推進するため、まずは広報活動の現状と課題を整理し、小平市に最も適したプロモーションのあり方を検討している段階との回答がありました。「基本戦略」については「現時点ではイメージしていない」としつつも、将来的な可能性を示唆しました。 職員の「広報マインド」を醸成するための研修も、外部講師を招くなどして強化していますが、専門人材の登用についても、他市の先進事例を参考に、どのような形で活用できるか検討していくとの回答がありました。
市長が掲げる「戦略的広報」を本格的に進めるには、プロフェッショナルの視点と専門知識が不可欠です。広報活動の現状と課題を整理することは重要ですが、その次のステップとして、コミュニケーション戦略、マーケティング戦略やデータ分析等の専門性が求められる場面が必ず出てきます。
市からは、職員研修の強化について言及がありましが、SNSの効果的な運用に向けた専任担当者の設置や広報専門人材の登用など、一歩踏み出した行動が必要ではないでしょうか。専門家の知見を借りながら、スピード感をもって施策を推進していくことが、今、最も求められていると考えます。
シティプロモーション専用の情報発信チャネル。必要では?



シティプロモーションの専門サイトやSNSを開設してはどうか?
- 行政情報とシティプロモーション情報が混在すると、ユーザーは求めている情報にたどり着きにくくなる
- 施策の背景にある「思い」や「日常の風景」をリアルタイムに発信するば、エンゲージメントを高められる
これらの理由から、シティプロモーション専用のウェブサイトやSNSアカウントの開設が必要だと提言しました。
市の答弁から見えたこと
現時点では専用サイトやアカウントの開設は考えておらず、既存のチャネルを強化し、ターゲットに合わせた情報発信に努める旨の答弁がありました。
市が既存のウェブサイトやSNSアカウントの活用を重視しているのであれば、私はその情報発信の最適化を強く求めました。
SNSにはそれぞれ独自の特性があります。例えば、Instagramでは写真やイラストで視覚的に訴える投稿が、またX(旧Twitter)のような速報性の高いプラットフォームでは、更新頻度を上げ、リアルタイムな情報を発信することが重要です。こうした各メディアの特性を最大限に活かすことで、市民の関心を引きつけ、小平市の魅力をより効果的に伝えられると考えます。
ウェブサイトをもっとわかりやすく、もっと便利に



ウェブサイトなど、わかりやすさを追求する取組を
現状の本市ホームページは言葉の使い方や必要な情報に辿り着きにくいなどの課題があり、まだ改善の余地があります。是非とも、この点を段階的にでも改善していただきたいとの思いから以下の提案をしました。
- わかりやすい市の情報発信に向け「UXライティング」の導入すべき
- 「AIラジオ」など、テキスト以外の情報発信のための手法を導入すべき
- ウェブサイトへの「AIナビゲーターやAIによる対話型検索機能」を導入すべき
「UXライティング」とは、ウェブサイトやアプリなどのデジタルサービスにおいて、ユーザーが快適に迷うことなく目的を達成できるよう、「言葉」をデザインする手法です。単に情報を伝えるだけでなく、ユーザー体験(UX)全体を向上させることを目的としています。今回の議論は、ガブテック東京のこちらの記事も参考にしました。参考記事:「UXライティング」で変わる行政の情報発信 | ガブテック東京
「AIラジオ」ですが、山形県大石田町では、GoogleのAIサービスを利用した「AIラジオ」を試験的に提供しています。これは、町の制度などの行政情報を、AIがラジオ風の音声に要約して配信する新しい取り組みです。スマートフォンやパソコンから24時間いつでも、手軽に音声で情報を得ることができます。実際の音声配信はこちらから聞くことができます。
「AIナビゲーター」は、町田市がオンラインサービスへの玄関口となる「バーチャル市役所ポータル」に実装している生成AIサービスです。
このAIナビゲーターは、ユーザーからの「どんな手続きが必要なの?」といった質問に答え、必要な行政手続きやオンラインサービスへのアクセス方法を案内してくれる仕組みです。これにより、市民は知りたい情報にスムーズにたどり着くことができます。
詳細は、町田市のバーチャル市役所ポータル「まちだDXラボ Machi-door」でご覧いただけます。
市の答弁から見えたこと
UXライティングの重要性については、市側も認識しており、GovTech東京のサポートも活用し、検討を進めていくとの回答がありました。真に利便性の高い市民サービスの実現には、UX(ユーザーエクスペリエンス)の改善が不可欠です。生成AIを活用すれば、UXライティングの視点で市民にとって分かりやすい表現に書き直すことも可能です。ぜひ早期の導入を望みます。ぜひ早期の導入を望みます。
AIラジオをはじめとするテキスト以外の表現手法については、他自治体の事例を参考に研究段階にとどまっています。デジタル政策参与の助言も求め、スモールスタート・スモールサクセスで新たな取り組みを進めていただきたいと考えます。
AIナビゲーションや生成AIを活用した対話型検索の導入については、ホームページのリニューアルを控える中で、費用対効果を含めた調査研究を進めていくとの回答がありました。
「住民票を移したい」といった自然な言葉から必要な情報にたどり着ける対話型検索は、単なる機能追加ではありません。技術の進歩により、検索強化生成(RAG)のような手法を使えば、正確性の向上が期待できます。また、問い合わせの減少によるコスト削減効果も得られます。
研究段階から一歩進め、段階的にでも具体的な検討を進めるべきです。引き続き、このテーマを取り上げていきます。
AI検索時代に備える



AI検索など、新たな技術の普及に対応する取組を
- AI検索対策に、生成AIが市の情報を正しく認識し、信頼できる情報源として引用できる環境を整えるべき
「AI検索」とは、AIを活用して、ユーザーの意図や文脈を理解し、最適な検索結果を提供する検索システムです。キーワードに合致するウェブページのリンクを一覧表示する従来の検索エンジンとは異なり、AIが複数の情報源から必要な情報をまとめて、直接的な回答として提示します。情報収集の効率化、複雑な質問への対応、検索方法の多様化などへの対応といったメリットがある一方、AIが回答を直接提示(いわゆる「ゼロクリック検索」)することで、ウェブサイト運営者は訪問者やクリック率の低下に直面する可能性もあります。(ちなみにこの解説文章の一部は、GoogleのAIモードに、「AI検索とは?」と聞いて作成されたものです)
AI検索の普及により、ユーザーは市役所のウェブサイトを訪問することなく、AIの回答画面で情報を完結させてしまうことも想定されます。この状況下では、市の情報がAIに正しく認識・引用されないと、不正確な情報が市民に届く危険性があります。この課題に対応するため、ウェブサイトの全面改修を待つのではなく、AIが理解しやすい情報設計を段階的に進めるべきだと訴えました。
市の答弁から見えたこと
現在、小平市は、AIが市のウェブサイト情報を正確に読み取れるよう、「情報の整理」や「AIの特性を理解した情報作成」が重要だと認識しています。しかし、具体的な対策はまだ「研究段階」にとどまっています。AIは急速に進化しており、待ったなしの状況です。市民の皆さんに正確な情報を迅速に届けるためには、この「研究」の段階から一歩踏み出し、具体的な行動を始める必要があります。
実は、AIが理解しやすいようにウェブサイトを整えることは、私たち人間にとっても大きなメリットがあります。例えば、
- 「UXライティング」:分かりやすく、迷わない文章作り。
- 「AIに優しい情報設計」:キーワードを含む見出しや簡潔なFAQなど、構造化された情報。
これらは、結果として誰もが使いやすいウェブサイトを作り出すことにつながります。「AIにも理解されやすい情報は、人にも優しい」という考え方を大切にし、デジタル技術を積極的に活用することで、市民の皆さんは必要な情報を素早く手に入れ、市役所の業務も効率化します。
私はこれからも、市の広報活動が「研究段階」に留まることなく、市民生活の利便性向上に直結する具体的な取り組みを、段階的にでも実行していくよう、強く提言し続けます。
結びに:「選ばれるまち」を目指して
小平市が「選ばれるまち」となるためには、広報やシティプロモーションを強化し、その魅力をわかりやすく、効果的に伝えることが不可欠です。そのためには、「人口流入」や「企業誘致」といった具体的な波及効果を見据えた目標(ゴール)設定が欠かせません。抽象的なイメージ向上にとどまらず、戦略的広報を掲げるのであれば、その指針となる基本戦略の策定も必要不可欠です。
わかりやすい、効果的な情報発信のためには、ウェブサイトの改善や、SNSでの情報発信の改善が必要ではないでしょうか。今回はその1つとして、伝わり、動かす方法論であるUXライティングの導入を提言しました。市としてもその重要性を認識しており、一歩ずつではありますが、前向きな姿勢も見られました。しかし、技術の進化は非常に速く、課題は待ったなしです。例えば、AI検索の普及により、市役所のウェブサイトを訪れることなく情報が完結する「ゼロクリック検索」のリスクも高まっています。正確な情報を確実に市民に届けるには、「研究」の段階を早急に超え、具体的な施策へと移行しなければなりません。
今後、広報に関する先進自治体の視察や研究等を通じて、最新技術の活用事例や成功の知見をしっかりと学び、小平市が真に利便性の高い、魅力的なまちとなるよう、さらなる改善を求め、引き続きこのテーマを取り上げてまいります。
今回の一般質問の内容は、小平市議会のウェブサイトから動画でご覧いただけます。