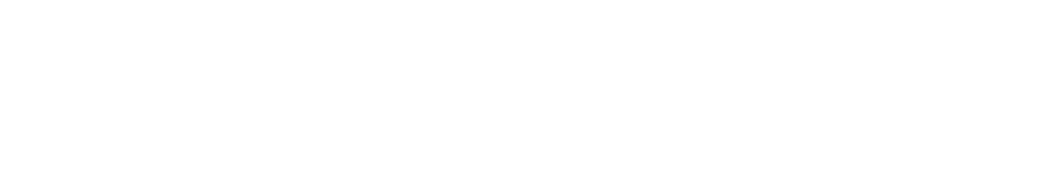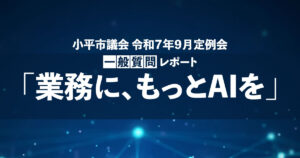行政の未来を拓く、AI活用のさらなる加速に向けて
私は、2年前に初めての一般質問で、いち早く「行政における生成AIの活用」を提言しました。当時、「取り入れるかどうか」の議論が中心だった生成AIは、今や一時的な流行ではなく、社会のあらゆる分野に浸透しつつあります。この2年間で、小平市でも生成AIの利用が始まり、その可能性と今後の課題が見えてきました。そして、議論の段階は「どう活用し、市民サービスや業務改善につなげるか」へと移っています。
私たちが直面する2040年問題をはじめとする社会課題に向きあう中で、持続可能な行政経営を確立し、多様な市民ニーズに応えるサービスを提供していくことは、次代への責任です。その基盤として、AIをはじめとする有効なテクノロジーを正しく、賢く活用していくための取り組みを加速させる段階にきています。
令和7年9月定例会では、こうした背景を踏まえ、本市におけるAI活用のさらなる進展と、それを支える体制整備について質問しました。この質問は、単なる新技術の導入に留まらず、将来にわたる行政のあり方そのものに関わる重要なテーマであると考えます。
小平市でのAI活用、いまどうなっている?
小平市では LoGo AI アシスタント bot版を導入し、職員の業務に活用しています。
- 利用者数:2年間で 58人 → 2,694人 に増加
- 利用率:全職員の約2割以上が利用
- 活用内容:文書要約、挨拶文作成、Excelの使い方検索など
現状の活用内容は、業務効率化につながるものではありますが、まだまだ活用の伸びしろがあると考えます。

もっと幅広い分野でAIを活用できるはず。
- 政策立案におけるデータ収集や分析、市民向け広報の強化といった分野でもAIの利活用を進め、市の課題解決に活かすべき。
- AIを「効率化ツール」としてだけでなくワクワクする未来像を描いて活用すべき。
市の答弁から見えたこと
市は「業務効率化に貢献している」と評価し、現在策定中の「(仮)DXビジョンこだいら2040」でも、AI活用は効率化の観点で位置付けられているとの答弁がありました。DXビジョンでは、創造的な未来を大胆に描くべきと提案しましたが、市からは「未来を見据えた技術活用を模索していく」との答弁がありました。
もちろん、未来を描き、そこから逆算して現在取り組むべき課題を考える過程では、現実的なハードルを意識し、目標を下方修正してしまうこともあるかもしれません。しかし、小平市のDX推進においては、現状維持にとどまらず、ぜひとも「チャレンジングな未来」を設定していただきたいと強く願います。
市民の皆様が「ワクワクする」ような、そして職員が「もっと創造的に働ける」ような、一歩先の未来像を具体的に掲げることが、真のDX推進の原動力になると確信しています。
新しいAIの導入は?



AIエージェントも視野に入れた多種のAIサービスを活用すべき。
生成AIは着実に進歩しています。他自治体では、議事録自動要約、画像生成、庁内FAQの構築など、多種のAIサービスを用いた多様な展開が始まっています。その観点から
- 本市も、GovTech東京が開発する生成AIプラットフォームをはじめ、新たなAIサービス、AIエージェントの活用を進めるべき。
と提案しました。
市の答弁から見えたこと
今回市からは、「GovTech東京」が開発する生成AIプラットフォームについて費用対効果を踏まえて検討する旨の答弁がありました。
新たなAI導入に向けた課題
現在小平市では「小平市生成AI利用ガイドライン」を定めており、その中ではLoGo AI アシスタントというサービスのみを利用可能としてます。今後、他の生成AIサービスを導入するためには、ルールの改訂が必要です。私の指摘と提案は
- 今のルールでは、特定のAIツール以外は業務で使うことが禁止されている一方、私たちのパソコンやスマートフォンにはAI機能が標準で搭載され始めており、意図せず業務で使ってしまう状況も起こりえるため、早急なガイドラインの見直しが必要。
- 技術革新が早い分野であり、新たなサービスの利用を妨げないように、「何ならつかえるのか」ではなく「どんなものは使ってはいけないか」を明確にするなど、時代に合わせたガイドラインとすべき。
この提案に対し、「(仮)DXビジョンこだいら2040」の策定とあわせて検討するとの答弁がありました。是非とも実効性のあるガイドラインへの早急な見直しを求めます。
AIを使いこなすための業務の根本的な見直しを



人が担う業務とAIに任せられる業務の整理・洗い出し、業務のやり方そのものを見直しを。
AIはあくまで便利な道具であり、それ自体が変革を生み出すわけではありません。確かに業務の一部にAIを導入すれば、表面的な効率化は実現するかもしれません。しかしながら、持続可能な行政や真に便利な市民サービスの実現には、業務の抜本的な再設計である「BPR」と「アナログ規制の見直し」が不可欠です。
「BPR」とは、ビジネス・プロセス・リエンジニアリングの頭文字をとったもので、自治体におけるBPRでは、行政サービスの提供方法や内部業務の進め方を、従来の慣習にとらわれずに根本から見直し、再構築する取り組みのことです。少子高齢化による職員不足や、住民ニーズの多様化といった課題に対応するために、行政サービスの質を向上させ、業務を効率化することを目的としています。
「アナログ規制の見直し」とは、時代にそぐわなくなった「対面」や「書面」、「目視」などを前提とした古いルールを、デジタル技術を活用できるように改正する取り組みです。これにより、行政手続きや業務の効率化、コスト削減、住民や事業者の利便性向上などを目指します。アナログ規制の見直しにより、働き方の多様化、コスト削減、業務効率化、利便性の向上などの効果が見込まれています
前回の令和7年6月定例会でアナログ規制について取り上げた際、「国の指針を参考に」との答弁がありました。また、昨年12月定例会での答弁では、DX推進リーダーは「デジタルツールを活用し、担当業務のDXやBPRを主導できる人材」とされ、現在10名が配置されています。このことを踏まえ、
- BPRやアナログ規制の見直しを、DX推進リーダーが主導して進めるべきだが、AIやAIエージェントを活用するための、BPRや業務フローの構築、アナログ規制の整理も含めて主導できる状況にあるのか。
- デジタル庁では地方自治体向けに、生成AIを活用したアナログ規制の見直しについてのワークショップを開催したが、本市も参加のチャンスがあれば積極的に活用すべき。
と提案・質問しました。
市の答弁から見えたこと
市では、BPRに関しての研修も進めており、業務改善計画や実施状況を自らの業務で活かせるよう行っているとの答弁がありました。ただし、ノウハウの蓄積は現状これからであり、生成AIを活用したアナログ規制の見直しなど、デジタル庁への職員派遣により最新情報を入手できる状況にあり、ワークショップへの参加も検討していく旨の答弁もありましたが、外部の専門的な知見を取り入れ、早急に取組を進めるべきだと考えます。BPRとアナログ規制の見直しについては、手続きのオンライン化などにも必要なテーマであるため、今後も引き続き取り上げてまいります。
AI人材をどう育てるか? 民間等との連携は?



AI 活⽤に向けた職員のスキル向上のための研修や⼈材育成の取組状況は?
現状、まだまだAI活用のノウハウの蓄積など、その活用に向けた体制整備は十分ではありません。そこで今回は、人材育成や風土づくりに焦点を当てて、以下の提案をしました。
- 若手職員が知識をベテランに共有する仕組み作り(リバースメンタリングなど)を取り入れてはどうか。
- 全庁的な生成AI活用研修で、新たな働き方・サービス創出を体験的に学ぶべき。
- 民間企業等、外部との積極的な連携で、行政サービスの質向上とイノベーションを。
市の答弁から見えたこと
DX推進リーダーの育成研修を実施しており、今後リバースメンタリングなども視野に入れた取り組みについて検討を進める旨の答弁がありました。 外部連携については、GovTech東京のスポット相談やプロジェクト型伴走サポートを引き続き活用していく方針が示されました。
最高AI責任者(CAIO)の登用など、AI活用の責任体制を整えるべきでは?



最高AI責任者(CAIO)を設置し、CAIOの補佐ともなる専門人材を登用してはどうか?
- 小平市でもAI活用の責任者であらう「最高AI責任者(CAIO)」を明確にし、専門知識を持つ人材を積極的に登用すべき。
- CAIOの補佐等を担うAI活用の専門人材の登用を
国も自治体に「最高AI責任者(CAIO)」という専門職を置くことを求める方針を示しています。それを受けて、本誌でも責任体制の整備に関する提案を行い、さらに国の動向を待つだけでなく、
- 必要な専門人材を主体的に描くこと
- 他自治体や関係機関との人材共有の可能性を探ること
を求めました。
市の答弁から見えたこと
これらの提案に対して市は、今後の生成AIの効果的な活用を検討する際に、AI戦略立案、リスク管理、法令遵守や倫理などに関わる専門知識を持つ人材が必要になると考えられる。総務省の動向も踏まえ、CAIOの設置に関しても今後検討を進める旨の答弁がありました。
本市の第2期経営方針推進プログラム No.21でも、DXを含む人材育成・確保に関する新方針の策定が本年度の課題とされています。外部人材の登用が難しい場合には、DX推進リーダーに上位研修の機会を与える、あるいは現在デジタル庁に出向している職員など、既存人材をさらに活用・育成することも必要です。単なる方針にとどめず、具体的な施策を早急に実行に移すべきと考えます。
結びに: ワクワクする「小平の未来」、「未来の小平」を創る
AIの進化は目覚ましく、単なる「研究」に留まることなく、具体的な行動へと迅速に一歩を踏み出すスピード感が今、求められています。
私は、小平市がAIを単なる効率化の道具としてではなく、「職員がもっと便利に、そして創造的に働ける」ような環境を創り、「市民にとって、より便利でワクワクするサービスが生まれる」ような未来を創るべきだと強く考えます。
これからも、科学者としての技術への理解と探求心、そして未来を見据える視点を強みに、小平市のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させます。常に最先端技術の動向を追い、先進自治体の事例を研究することで、小平市がAIを活用した次世代の行政をリードするための具体的な道筋を示します。市民の皆様にとって、より便利で質の高い行政サービスが実現できるよう、引き続き、AI活用策の提言と実現に全力で取り組みます。
今回の一般質問の内容は、小平市議会のウェブサイトから動画でご覧いただけます。